はじめに
近年、あん摩マッサージ指圧療法(以下「マッサージ」)の受療率は上昇傾向にある一方、鍼灸療法は減少傾向が続いています。
この変化は、現代社会におけるストレス増加や健康維持への関心の高まりを反映していると考えられます。
本記事では、国内の20〜99歳の男女1,214人を対象とした調査結果をもとに、受療率の変化や背景、課題について解説します。
あん摩マッサージ指圧療法、鍼灸療法に対する受療者の評価に関する調査(前編)1.6MB
マッサージの受療率は上昇傾向

マッサージは、疲労回復やリラクゼーションを目的とした施術として、多くの人々に利用されています。
2018年度の調査によると、マッサージの年間受療率は17.3%から20.1%に増加し、2.8%の上昇を示しました。
また、「1年以上前に受けたことがある」と答えた経験者も41.9%から43.9%に増加しています。
特に疲労回復を目的とする受療者が多い点が特徴です。
ポイント
マッサージの年間受療率は20.1%に達し、疲労回復を求める人々から高い支持を得ています。
鍼灸の受療率の低下

一方で、鍼灸の受療率は減少傾向にあります。
2002年度から2012年度までの間、鍼灸の受療率はほぼ7.5%前後で推移していましたが、2017年度には4.6%、2018年度には4.0%まで低下しました。
この受療率の低下は、需要に対する供給量の増加や施術者の質の低下が要因として指摘されています。
背景として、施術者数の増加による競争激化と施術者の質に対する不安が挙げられます。
特に施術の質のばらつきは、受療率低下の大きな要因と考えられます。
ポイント
鍼灸の受療率は4.0%まで低下し、施術者の質向上が喫緊の課題です。
施術者の質と医療の質

調査では、施術者の技術や対応が医療の質に直結することが明らかになっています。
特に「あなたの状態をよく説明してくれる」という評価は、施術回数が多いほど高評価となる傾向が見られました。
例として、10回以上受療した人の52.1%が「とてもあてはまる」と回答しています。
これは、施術者が丁寧に説明し、信頼関係を築くことで満足度が向上することを示しています。
ポイント
高い技術と丁寧な説明は、受療者の信頼と満足度を高める鍵です。
まとめ
マッサージは現代社会において、疲労回復や心身のリフレッシュに大きく貢献しています。
一方、鍼灸療法は受療率低下が課題であり、施術者の技術力・対応力の向上が求められます。
今後は、以下の項目が両療法の信頼性と受療率向上に不可欠です。
- 施術の質向上
- 受療者が安心できる環境づくり
- 正確で分かりやすい説明の徹底
世界で認められている鍼灸マッサージの効果
鍼灸マッサージの有効性は世界でも認められています。こちらの記事を参考にしてください。
あはき取得できる学校を選択する







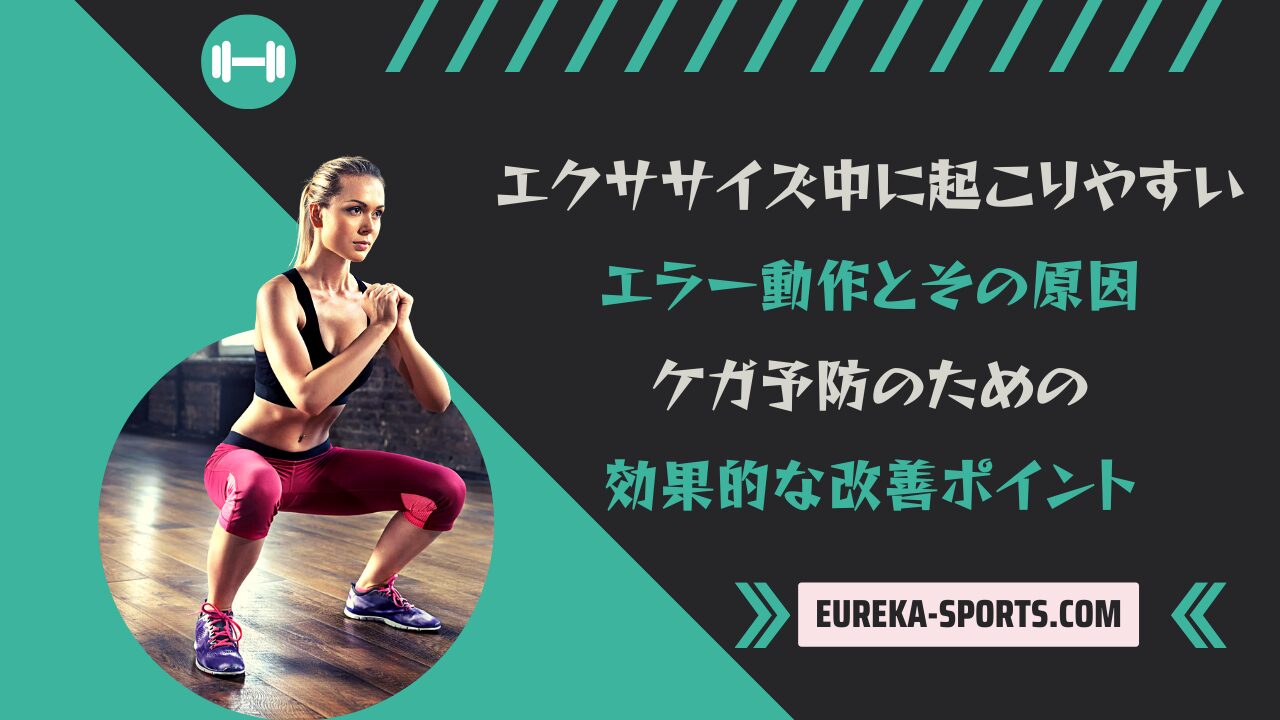
コメント